はじめに|分配金=自動で再投資されると思っていた

「高配当でコスパよし!ETFって最強じゃん!」
そんなふうに思って、米国ETFに飛びついた数か月前の私は、またちょっと浮かれていました。
しかし、実際に分配金を受け取ったとき
―― 思わず「え?これどうすればいいの……?」と戸惑ってしまいました。
そう、ETFの分配金は自動で再投資されないんです。
この記事では、私が初めて米国ETFを買って、分配金で少しだけ後悔した体験をまとめます。
同じように「ETFを買ってみたいな」と思っている方の参考になればうれしいです。
▼「分配金と配当金って何が違うの?」と思った方はこちらの動画がわかりやすかったです。
なぜETFを買ったのか|VYMとSPYDに惹かれた理由

私が買ったのは、
- VYM(バンガード 米国高配当株式ETF)
- SPYD(SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF)の2つです。
理由は単純で、「高配当で投資コストが安い」と聞いたからです。
高配当って、なんだか魅力的に聞こえちゃいますよね。
「定期的に分配金がもらえる」
「資産形成にもなる」
という情報を YouTubeやブログで見かけて、
「これだ!」と思いました。
ちょうどNISA口座の枠が残っていたこともあって、 VYMを10株、SPYDを10株買ってみました。
分配金が入ってきた!……でもちょっと困惑

初めての分配金が入ってきたのは、2025年6月のことです。
- VYM:6月26日入金/7.76ドル
- SPYD:6月30日入金/4.50ドル
合計で12.26ドル(日本円で約1,900円ほど)になりました。
「おお〜!分配金がきた!」 その瞬間は正直うれしかったです。
でも、すぐにこう思いました。

「……ドル?この少額、どうすれば?」
私は「分配金って、自動的に再投資されるもの」だと勘違いしていました。
ですがETFは、投資信託のように“再投資型”が選べないんです。
調べてみてわかったETFの仕組み

慌てて調べてみたところ、すぐに見つかりました。
ETFの分配金は、自動で再投資されません。
つまり、分配金を受け取ったら、
- ドルのまま証券口座に入る
- 自分で手動でETFを買い直す必要がある
- 少額だと再投資しにくい
ということなんです。
投資信託のように、自動的に分配金が再投資されていくスタイルとはまったく違いました。
参考:Yahoo!ファイナンス 米国株やETF株の分配金の再投資はどうやるの?
投資信託との違い|ズボラには投資信託が向いている?
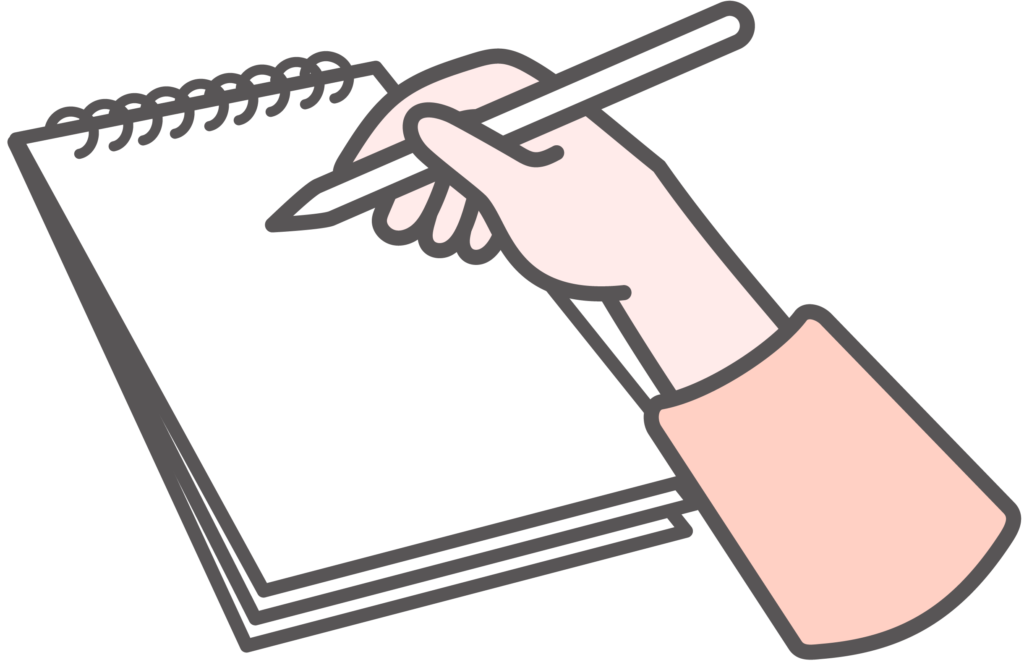
実際に体験してみて思ったのは、私のようなズボラな人に
ETFはちょっと手間がかかるということです。
投資信託であれば、最初に「分配金再投資型」を選んでおけば、 あとは何もしなくても自動で再投資されます。
複利効果も自然に働くので、長期運用にはぴったりです。
一方、ETFは以下のような違いがあります。
- 分配金が現金で入ってきます → 円でもらうか、ドルでもらうかを自分で選びます。
- 再投資するには、自分で手続きが必要です → 「この分配金で何を買うか」「いつ買うか」を自分で判断しなければいけません。
- 買うタイミングも考える必要があります → ETFの価格は常に変動しているため、「今買っていいのか?」という判断も求められます。
つまり、ETFは “自動でおまかせ” ができない世界なんです。
私はこの違いをよく理解しないままETFを買ってしまい、 「投資信託って、実はものすごくラクだったんだな」と改めて実感しました。
▼投資信託とETFの違いはこの動画がわかりやすかったです。
今後の方針|ETFは “放置” メインは投資信託へ

せっかく買ったVYMとSPYDは、売却せずこのまま所有するつもりです。
受け取ったドルの分配金もそのまま置いておいて、 またETFを買うときの資金にしようかなと思っています。
今後のメインは投資信託+日本株にしようと思います。
これからETFを買う初心者さんへ|ちょっとだけ準備しておこう
ETFの情報を見ていると、「高配当」「低コスト」といったキラキラしたメリットがたくさん出てきます。
もちろん、それは間違っていませんし、好きなタイミングで売買できる優れた商品だと思います。
でも――
- 分配金が自動で再投資されない
- 少額の分配金だと、使いにくい
- 為替手数料や税金も地味にかかる
という現実もあるのです。
だからこそ、買う前にちょっとだけ調べておくことが本当に大事だと思います。
私はこの体験で、やっと理解できました。
おわりに|“やってみる”ことが一番の学びになる
今回の「再投資できなかった」体験は、投資の世界で見ればごく小さな出来事です。
でも、私にとっては「投資って、思ってたより奥が深いんだな」と気づけた大きなきっかけでした。
この経験をもとに、今後も“ラクな暮らし”と“資産形成”をうまく両立していけたらいいなと思っています。
この記事が、これからETFを始めてみようかなと思っている方の参考になればうれしいです。

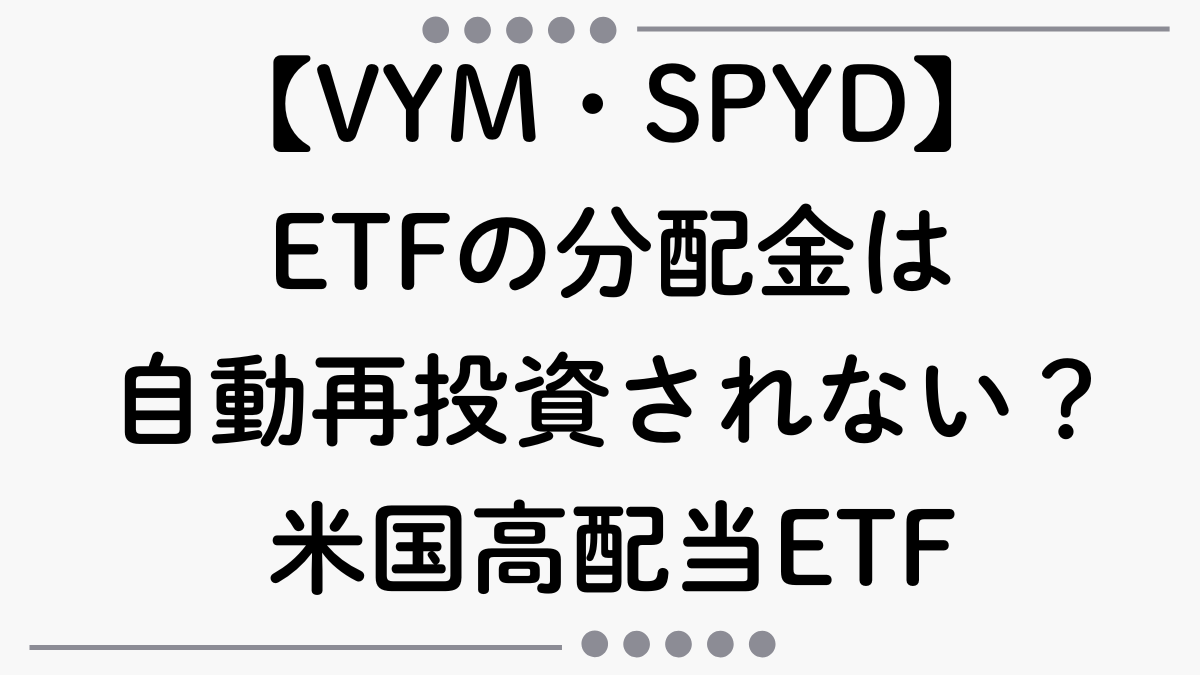
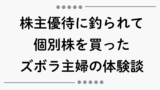
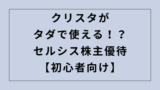
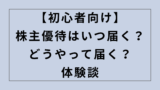
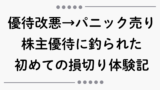

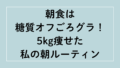
コメント